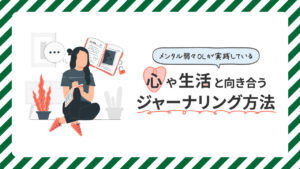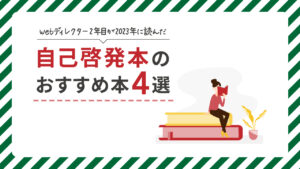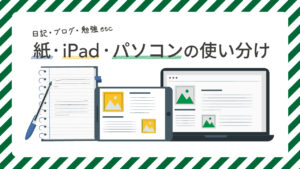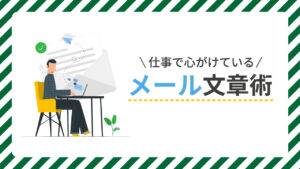本記事には広告やプロモーションが含まれていることがあります
上司やチームからフィードバックをもらいやすい依頼方法と準備のコツ


こんにちは、おんたまです。
仕事を進める中で、上司やチームメンバーに「ちょっと見てもらいたいな」「意見を聞きたいな」という場面は多いですよね。
ただ、いざ相談しようとすると──
- 忙しそうで声をかけにくい
- どう伝えればいいか分からずモヤモヤする
- 相談したのに思ったような答えがもらえなかった
こんな経験をしたことはないでしょうか?
実はフィードバックをスムーズにもらうには「事前準備」と「相談の場での工夫」が大きなカギになると感じています。この記事では、私がWebディレクターとして実践している具体的な方法をご紹介します!
- 上司やチームメンバーに相談するとき、どう依頼すればいいか悩んでいる方
- 複数のメンバーと協力して仕事を進めている方
- フィードバックを効率よくもらいたいけれど、依頼の仕方に自信がない方
- 打ち合わせや相談が長引きやすく、もっとスムーズに進めたいと思っている方
フィードバックを依頼する前に準備が必要な理由
依頼が曖昧だと正しいフィードバックが得られない
「ちょっと見てもらえますか?」と声をかけただけだと、相手は「どこを見ればいいのか」「何を答えればいいのか」が分かりません。
そうすると相談内容の把握から始まるので会話が長引いたり、うまく伝わらず期待していた答えと違う方向に進んでしまうこともあります。
一方で、見てほしいポイントや相談の目的をあらかじめ整理して伝えることで、相手にも時間があれば事前に準備をしたり考えをまとめておくことができ、的確なアドバイスを返してもらいやすくなります。
準備があると上司やメンバーの負担を減らせる
誰かに相談するということは、相手の時間を使うことでもあります。
どんな内容でどれくらいの時間がかかりそうかを事前に伝えておけば、相手もスケジュールを調整しやすく、心理的な負担もぐっと減ります。
「話を円滑に進めやすい人」と見てもらえることは、フィードバックの場面だけでなく、さまざまなやり取りで頼りにされる第一歩です。そのためにも相談する準備をしておくことは大切だと感じています。
フィードバック依頼前の準備
まずは自分で調べたり考えて仮説を持つ
相談をする前に大切なのは、まず自分で調べたり考えたりして仮説を持っておくことです。
「分からないから全部相手に聞く」という姿勢では、自分で考えて進める力がなかなか身につきません。相談は相手に答えを丸投げする場ではなく、自分の考えを整理し知見を広げるきっかけとして活用するものと捉えるのがおすすめです。
また、相手にとっても仮説を提示してもらえた方が答えやすくなります。ゼロから考えるのは負担が大きいですが、「A案とB案を考えてみました。個人的には〇〇という理由でA案が良いと考えましたがアドバイスをいただけますか?」と聞かれれば、Yes/Noや比較から話を始められます。その分スムーズに具体的な意見を聞きやすくなります。
相談の打診時に概要と想定所要時間を伝える
緊急の用件でなければその場でいきなり「ちょっと相談いいですか?」と話を始めるのではなく、まずは相談時間の打診から行うのがおすすめです。
その際に「どんな内容を相談したいのか」と「どのくらい時間がかかりそうか」を伝えておくと、相手は心構えができます。たとえば「◯◯案件の方向性について10分ほど確認したいです」「作成した資料の一部について30分ほどご相談させてください」といった形です。
もちろん、実際には想定した時間より長引いたり、話が広がって別のテーマに発展することもあります。それでも最初に概要と所要時間を伝えておくことで、相談を受ける側は「この内容ならこういう質問が来そうかな」とシミュレーションができます。結果として、答えやすさや議論の質もぐっと高まります。
ちなみに私の職場ではチャットでのコミュニケーションが主流なので、以下のようにテキストで伝えることが多いです。
📌 打診連絡の例
お疲れ様です。以下内容の相談をお願いしたく思います。
<相談事項>
・A社LP制作の進捗共有とスケジュール調整について
・◯◯キャンペーンの提案資料の作成相談
時間は30分想定ですがご都合いかがでしょうか?
A社へ来週には連絡をしたいため、明日までの間にお時間をいただけると大変助かります!
相談内容をドキュメントで整理する
相談したい内容が複雑だったり複数のテーマにまたがる場合は、一度ドキュメントに書き起こして整理しておくのがおすすめです。
「課題」「背景」「確認したい点」といった形で書き出すと自分自身も内容を再認識できますし、相手にとっても状況を理解しやすくなります。その結果、相談の場がより効率的に進みやすくなります。
さらに整理した内容を相談時に画面共有しながら話すと、共通認識を持ちやすく話の行き違いや相談漏れを減らすことにもつながります。チーム内で共有する目的であれば完璧に整えた資料でなくても大丈夫かと思います。ざっくりとポイントを書き出してあるだけでも、会話の質はぐっと高まると感じています。
📌 相談内容の整理の例
<課題>
A社サイトのデザイン制作に入るタイミングが予定より遅延しそう
→クライアントからの素材提供が遅れている。進捗確認したところ再来週の提供になってしまいそうとのこと
<相談したい点>
以下対応で問題ないか、またクライアントへの連絡時に気を付けるべきことがあるか確認
・未提供の素材を扱うページの制作は後回しにして着手できるページからの制作スタートに切り替える
→デザイナーとクライアントには段取りを先に伝えていたので変更が入る旨を共有予定
フィードバックを受ける場での工夫
画面共有を活用する
相談の場では、自分のPC画面を共有しながら話すと話を整理しやすくなります。
たとえばWebサイトの制作や更新業務のように実際のサイトや制作物がある場合は、画面を見せながら進めることで「どの部分を指しているのか」が伝わりやすくなり、認識のズレも少なくなります。
また、Web制作に直接関わらない相談ごとであっても効果的です。先述した通り事前にまとめたメモを画面に映しながら話せば、聞き逃しを防ぎ、言葉で伝えきれなかった部分を補完できます。結果として相手にとっても理解しやすく、やり取りの精度が上がります。
複数人での打ち合わせでは議事録を残す
複数人での相談や内容が複雑になる場合には、話した内容を議事録として残しておくのが効果的です。相談はその場で完結せず、新たな進展や追加の確認が必要になることも多いため、過去のやりとりが記録に残っていると次の打ち合わせをスムーズに進めやすくなります。
メンバー内でフランクに相談している場面であれば必ずしも丁寧な議事録を作る必要はありませんが、メモベースでも記録しておくと後から振り返りや引用がしやすく、会話の土台として役立ちます。
例えば事前に相談内容をドキュメントでまとめていた場合は、そのドキュメントに話した内容を追記してメンバーへ共有していました。
📌 議事メモの例(事前に整理したドキュメントに追記するパターン)
※フィードバック内容は赤字で記載
<課題>
A社サイトのデザイン制作に入るタイミングが予定より遅延しそう
→クライアントからの素材提供が遅れている。進捗確認したところ再来週の提供になってしまいそうとのこと
<相談したい点>
以下対応で問題ないか、またクライアントへの連絡時に気を付けるべきことがあるか確認
・未提供の素材を扱うページの制作は後回しにして着手できるページからの制作スタートに切り替える
→デザイナーとクライアントには段取りを先に伝えていたので変更が入る旨を共有予定
→対応の方向性自体は問題なし。先方には素材提供の念押しもしておいた方がいいので、素材提供のデッドライン(10/5中)と、それ以上遅れる場合はリリース日自体の調整が必要な旨を伝える
まとめ
相談の場をうまく活かすためには、少しの工夫が大きな違いを生みます。仮説を持って臨むことや内容を整理して伝えること、画面を見せながら話すこと、必要に応じて議事録を残すこと――こうした積み重ねが、相談をより建設的で学びの多い時間にしてくれます。
もちろん、相談の規模や内容によっては必ずしもすべての準備が必要なわけではありません。ただ、相手に配慮をもって準備や会話を心がけることで、結果的に「この人とは話しやすい」と感じてもらいやすくなり、日常のコミュニケーション全般で良好な関係を築いていけるはずです。小さな工夫の積み重ねが、信頼や安心感につながっていくのだと思って私も引き続き精進していきたいと思います😌